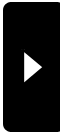その調子。
昔から歯医者さんが苦手だったのだが、いまのところは雰囲気や声色が明るく、あまりドキドキせずに通うことができている。
今日の定期健診でも、おそうじしてもらっているときに、「その調子でお願いしますね」の声。うれしい気持ちになって、次もそういってもらえるようにしたいなと思った。
ここ最近目にした記事やテレビ番組で感じたこととも重なった。
(自分の場合、機会は限られておりますが)自然にそういう声かけができるとは思えないので、引き出しの一番手間に「その調子」を入れておこう。
今日の定期健診でも、おそうじしてもらっているときに、「その調子でお願いしますね」の声。うれしい気持ちになって、次もそういってもらえるようにしたいなと思った。
ここ最近目にした記事やテレビ番組で感じたこととも重なった。
(自分の場合、機会は限られておりますが)自然にそういう声かけができるとは思えないので、引き出しの一番手間に「その調子」を入れておこう。
2022年11月16日 Posted by デイクリップ at 14:42 │Comments(0) │言葉
何かを決定するとき、一番大事なのはBGMだと思う。
普段、原稿を書く仕事のときは、ミニマルで反復的な音楽を聞きながら、ということが多い。周囲の情報や浮かんだ雑念に気持ちをあまり引っ張られずに済む(ような気がする)からだ。
最近、家族の暮らしぶりをやわらかく伝える原稿を何本か書いたのだけれど、オーガニックでゆったりめの音楽を聞きながらのほうがスムーズだった。仕上がりもその媒体の雰囲気にマッチするようなものになっていた(ように思う)。
昔、ある雑誌でザ・クロマニヨンズ(当時The High-Lows)の甲本ヒロトさんが、「何かを決定するとき、一番大事なのはBGMだと思う」と語っていた。いろいろな表現、芸術が、人々の生活にインスピレーションを与え、選択を左右しているが、耳に届く音もそのひとつだと。

[SNOOZER #031 2002.6]
気をゆるすと、耳にも目にも、前に進もうというきもちを削ぐような、不安やイライラを大きくするような情報ばかりが飛び込んでくる。自分たちがつくるもの、発信するものは、現状にひたり過ぎることも、根拠のない希望に寄りかかり過ぎることもなく、“ ふわっときもちを持ち上げるあたり ” を目指したい。
最近、家族の暮らしぶりをやわらかく伝える原稿を何本か書いたのだけれど、オーガニックでゆったりめの音楽を聞きながらのほうがスムーズだった。仕上がりもその媒体の雰囲気にマッチするようなものになっていた(ように思う)。
昔、ある雑誌でザ・クロマニヨンズ(当時The High-Lows)の甲本ヒロトさんが、「何かを決定するとき、一番大事なのはBGMだと思う」と語っていた。いろいろな表現、芸術が、人々の生活にインスピレーションを与え、選択を左右しているが、耳に届く音もそのひとつだと。
[SNOOZER #031 2002.6]
気をゆるすと、耳にも目にも、前に進もうというきもちを削ぐような、不安やイライラを大きくするような情報ばかりが飛び込んでくる。自分たちがつくるもの、発信するものは、現状にひたり過ぎることも、根拠のない希望に寄りかかり過ぎることもなく、“ ふわっときもちを持ち上げるあたり ” を目指したい。
2020年04月02日 Posted by デイクリップ at 21:23 │Comments(0) │言葉
「魅力ある日本」、「魅力ない私」。
朝、仕事場に到着して、時間があれば、TBSラジオ『森本毅郎スタンバイ』を聞く。先週、先々週と木曜ゲスト、東京大学名誉教授・月尾嘉男さんのお話を興味深く聞いた。
カーター政権の大統領補佐官を勤めた政治学者、ズビグネフ・ブレジンスキー氏は、1997年に発表した著書のなかで、ソビエト連邦を崩壊させ、アメリカが世界唯一の覇権国になったのは、世界一の軍事力、経済力、技術力とともに、世界の若者を魅了して止まない「文化力」を獲得したからだと述べている。その戦略を別角度から分析しているのが、クリントン政権の国防次官補を務めたジョセフ・ナイ氏で、これからの国家の重要な力は軍事力や経済力のようなハードパワーではなく、ソフトパワーになると提言。その本質は「魅力」と呼ばれるもので、必要とされる人材、物資、資金、情報などを “ 引き寄せる力 ” だと説明している。このあと、日本が有する魅力について、また反対に、魅力のなさについて、考察が続いていったが、上の冒頭部分が特に印象に残った。
ハードのパワーが極端に足りない私だが、まわりの方にこちらを向いてもらい、近づいてきてもらうだけの力も、まったくもって不足している。自然に身についていくもの、意識せずに染みだすものだと思うが、仕事や子育てや地域での活動などを通じて、少しでも増やせていけたらと思う。
カーター政権の大統領補佐官を勤めた政治学者、ズビグネフ・ブレジンスキー氏は、1997年に発表した著書のなかで、ソビエト連邦を崩壊させ、アメリカが世界唯一の覇権国になったのは、世界一の軍事力、経済力、技術力とともに、世界の若者を魅了して止まない「文化力」を獲得したからだと述べている。その戦略を別角度から分析しているのが、クリントン政権の国防次官補を務めたジョセフ・ナイ氏で、これからの国家の重要な力は軍事力や経済力のようなハードパワーではなく、ソフトパワーになると提言。その本質は「魅力」と呼ばれるもので、必要とされる人材、物資、資金、情報などを “ 引き寄せる力 ” だと説明している。このあと、日本が有する魅力について、また反対に、魅力のなさについて、考察が続いていったが、上の冒頭部分が特に印象に残った。
ハードのパワーが極端に足りない私だが、まわりの方にこちらを向いてもらい、近づいてきてもらうだけの力も、まったくもって不足している。自然に身についていくもの、意識せずに染みだすものだと思うが、仕事や子育てや地域での活動などを通じて、少しでも増やせていけたらと思う。
2019年01月22日 Posted by デイクリップ at 21:41 │Comments(0) │言葉
安いものにはワケがある。値段が張るものには物語がある。
息子の担任の先生から配られるHR通信。その一番の読者は、じつは私かもしれません。

こんなおっさんでも、気持ちを前向きにしてもらったり、背筋を伸ばしてもらったりしています。

きっと息子の心にも、栄養として蓄積されているはず(そう思いたい!)。

いろいろな先生がいて、スタイルもさまざまだと思いますが、少なくとも我が家(というか私)にとっては、ありがたい出会いをいただいたと感じています。
こんなおっさんでも、気持ちを前向きにしてもらったり、背筋を伸ばしてもらったりしています。
きっと息子の心にも、栄養として蓄積されているはず(そう思いたい!)。
いろいろな先生がいて、スタイルもさまざまだと思いますが、少なくとも我が家(というか私)にとっては、ありがたい出会いをいただいたと感じています。
2018年09月05日 Posted by デイクリップ at 12:26 │Comments(0) │言葉
面白くない原因を作っているのは第三者ではなくて、「自分」でしかないんですよ。
「気分転換に棚から1冊」シリーズです。

--------------「未来」っていうのは、この瞬間が作っているわけですよね。5分後の未来というのは、この瞬間が5分後を作っていく。だから一番大事なのは、たった今「現在」ってやつ。この「現在」を充実させてちゃんと味わっていくことが、未来を積み重ねて作っていくことになる。
--------------自分に興味を持つしかないんです。今の社会はみんな他人や外界に興味を持ち過ぎている。自分の不幸さ加減とか自分が面白くない原因をすべて経済や社会や学校や家庭に転化してしまっている。そうじゃなくって、その面白くない原因を作っているのは第三者ではなくて、「自分」でしかないんですよ。
--------------世の中の新しいことに対しての関心よりも、自分がまだやってないこと、誰かがやってるかもしれないけど自分にとっての新しいことが大切ですね。
--------------おいしいことばかりやっていると、またエグい問題が生じるんですよ。だから全く反対の辛いことをした方がいいって直感が働いたんです。人間ってある時期必ず辛いことを逃げないでどう対処するか、試される。
--------------言葉の上では駄目で、やっぱり実践しないと。この記事を読んでも頭の中で理解しただけでしかない。逆に行動さえしていれば、今言ったことは忘れてもいいんですよ。どう実行するかしかないんですよ。

--------------未来は向こうからやって来るもんじゃなくて、自分で作っていくものだと思いますね。
BARFOUT!(バァフアウト) vol.41 1999年1月17日発売
「1999 THE FUTURE?」特集内、横尾忠則さんの言葉より抜粋
--------------「未来」っていうのは、この瞬間が作っているわけですよね。5分後の未来というのは、この瞬間が5分後を作っていく。だから一番大事なのは、たった今「現在」ってやつ。この「現在」を充実させてちゃんと味わっていくことが、未来を積み重ねて作っていくことになる。
--------------自分に興味を持つしかないんです。今の社会はみんな他人や外界に興味を持ち過ぎている。自分の不幸さ加減とか自分が面白くない原因をすべて経済や社会や学校や家庭に転化してしまっている。そうじゃなくって、その面白くない原因を作っているのは第三者ではなくて、「自分」でしかないんですよ。
--------------世の中の新しいことに対しての関心よりも、自分がまだやってないこと、誰かがやってるかもしれないけど自分にとっての新しいことが大切ですね。
--------------おいしいことばかりやっていると、またエグい問題が生じるんですよ。だから全く反対の辛いことをした方がいいって直感が働いたんです。人間ってある時期必ず辛いことを逃げないでどう対処するか、試される。
--------------言葉の上では駄目で、やっぱり実践しないと。この記事を読んでも頭の中で理解しただけでしかない。逆に行動さえしていれば、今言ったことは忘れてもいいんですよ。どう実行するかしかないんですよ。
--------------未来は向こうからやって来るもんじゃなくて、自分で作っていくものだと思いますね。
BARFOUT!(バァフアウト) vol.41 1999年1月17日発売
「1999 THE FUTURE?」特集内、横尾忠則さんの言葉より抜粋
2018年01月24日 Posted by デイクリップ at 15:00 │Comments(0) │言葉
あたたかい人には あたたかい人が集まる
先日、撮影に寄らせていただいた、 『日本料理 五平』さん に掛けられていた、神田川俊郎さんの言葉。

もし、マイナスの感情を抱かざるを得ない誰かが身の回りにいるのなら、それは自分に問題があるからなのかもしれませんね。
もし、マイナスの感情を抱かざるを得ない誰かが身の回りにいるのなら、それは自分に問題があるからなのかもしれませんね。
2017年10月13日 Posted by デイクリップ at 18:07 │Comments(0) │言葉
人にしてもらったことは。
「人にしてあげたことは、すぐ忘れろ。
人にしてもらったことは、生涯忘れるな」
石原裕次郎
木曜午後のお打ち合わせで、
「なんとか月曜にほしいんですが、
ある印刷会社さんに2週間はかかるといわれちゃって」
と、担当者さん。
校正は遅い時間までとなり、
間に合いそうな印刷所を探して、
それぞれに依頼することになりましたが、
本日、朝一にお納めすることができ、
「助かりました」といっていただきました。
「おれらの仕事、あとまわしでいいからさ!」
そういって今回紹介してくださった社長さんからのご依頼、
いつも以上に気持ちを込めて、と思います。
2016年09月05日 Posted by デイクリップ at 14:26 │Comments(0) │その他の仕事│言葉
ひとつがすべて。
「 つくり手は毎日たくさんつくりますが、
食べてくれる方にとっては、その1つがすべて。
食べてくれる方のことを考えて、この1つをつくります 」
明治39年創業の菓子店にて、
大切にしていることは?、の問いに4代目の言葉。

受け継がれているのは、そんな姿勢。
食べてくれる方にとっては、その1つがすべて。
食べてくれる方のことを考えて、この1つをつくります 」
明治39年創業の菓子店にて、
大切にしていることは?、の問いに4代目の言葉。
受け継がれているのは、そんな姿勢。